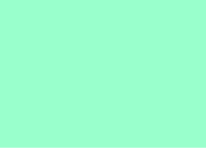2015年2月7日(土)に開催された新春企画では、
「いま貧困を問う 豊かな社会をつくるために
~現場から見えてくる貧困を通してこれからの課題をさぐる~」
をテーマに、以下の6名からの話題提供のもと、伊藤文人氏のコーディネートにより、フロアと討論を行いました。
・成年後見の現場から・・富松玲香氏(知多地域成年後見センター)
・学生のカウンセリングの現場から・・
安江理世氏(トライデントコンピュータ専門学校)
・国民健康保険の窓口から・・津田康裕氏(名古屋市中村区役所)
・福祉で働く人たちの労働組合から・・
田中理華氏(福祉保育労・ぐみの木保育園)
・障がい者支援の現場から・・大野健志氏(さくらんぼ作業所)
・生活保護バッシングと運動上の課題・・山田壮志郎氏(日本福祉大学)
富松氏からは、知多半島では五市五町の行政がNPO法人へ成年後見制度に関する業務を委託することにより、低所得や身寄りがいない方でも必要であれば成年後見制度が利用しやすい土壌があることについて報告され、保証人等の関係で居住場所がみつからず社会的入院が継続してしまうこと、居場所がないよりマシという視点で劣悪な居住環境におかれたままになることが多々あると述べられました。
安江氏からは、リーマンショック以降、経済的理由で退学する学生が増加したと報告がありました。また、格差が、手段を選ばず自分の位置を保つことに重きをおいてしまうこと、今の社会にだめな自分を受け入れてくれる場がないことが、息苦しさをもたらしているのではないかという報告がありました。
津田氏からは、国民健康保険、国民年金、協会けんぽ、厚生年金保険料計算比較表を用いて、収入がゼロでも均等割の部分を支払うこと、収入があっても1割は保険料として支払わねばならない現状について報告がありました。社会保障の一環で始まった制度が、現在払えない人は守らないという相互扶助に変わってしまっているのではないかという問題提起がなされました。
田中氏からは、ぐみの木保育園の労働組合は活動が活発で、日々の保育だけでなく、保育環境を整備していくために毎年市に要望書を提出していることについて報告がありました。男性保育士は経済的理由で退職を余儀なくされることがあり、働く人の生活が守れるような業界にすることの必要性について語られました。
大野氏からは、障害者自立支援法の成立により応益負担と自己責任を求められ、お金が払えないのでサービス利用をやめた障害者が増えたこと、そのため、生活保護制度利用支援を行ってきたと報告がありました。その他、きょうされん一万人アンケートの結果、障害者の99%が年収200万円以下であり、経済的貧困が可能性や発達の権利を侵害していると報告がありました。
山田氏からは、インターネット調査結果をもとに、①「生活保護への不信感は不正受給問題とギャンブルによる保護費の費消に強く表れている」、②「不正受給に対する抵抗感が制度全般への不信感を招いている」、③「生活保護基準の引き下げは必ずしも世論の大勢となっていない可能性がある」、④「生活保護への不信感は、低所得層に強く表れているとはいえない」の4点を指摘されました。
後半の討論では生活保護の不正受給が実際少ないという正しい情報を伝えても反応がない現状についてどうしたらよいか、本当の意味での在宅生活とは何なのか、労働とは何なのか、賃労働がすべてのように言われてしまうこの社会情勢をどのように変えていったらよいか、格差はあってもよいと思っている人がどうして多いのか、などたくさんの意見が出て盛会でした。
世代や領域を超えて問い続けていくことが目的である学内学会にふさわしい新春企画となったと思います。話題提供してくださったみなさん、コーディネーターの伊藤さん、参加者のみなさんありがとうございました。

○開催日時:平成24年12月8日(土)
○参加人数:36名(初参加19名)
○報告者
・橋本市立紀見北中学校 大前雅司氏
・半田市社会福祉協議会 飯盛 満氏
・可知病院 松井勇太郎氏
・さくら総合病院 池谷鉄平氏
○内容
最初にアイスブレイクを行いました。2人1組でお互いの名前や職業、趣味などを聞き合い、それをもとに、相手を漢字一文字で表します。それをグループ内で他己紹介。「祭」「逞」など様々な漢字が飛び出し、「あっ!」という間に会場の雰囲気が和みました。
報告では、経験年数が1年目から7年目まで活躍されている4名の方に、現場実践について話して頂きました。大前氏からは、視覚障害のある教員としての授業の工夫について、松井氏からは、カンファレンスや勉強会への積極的な参加を通して組織の変革を目指していることについて、
 いと悩みについて意見交換をしました。ワールドカフェ方式は、「人と人が出会い、カフェのような気楽で自由な対話を通して、刺激し合い、新しい発見を生み出すこと」を目的としています。 各グループのファシリテーターが中心となり、テーマ「仕事のやりがいや苦労」について、意見を出し合いました。
いと悩みについて意見交換をしました。ワールドカフェ方式は、「人と人が出会い、カフェのような気楽で自由な対話を通して、刺激し合い、新しい発見を生み出すこと」を目的としています。 各グループのファシリテーターが中心となり、テーマ「仕事のやりがいや苦労」について、意見を出し合いました。
計3セットのグループワークを終え、最初にいたテーブルに戻ってみると、自分達が初めに出した言葉や意見がとても広がっていることに、歓声が上がりました。
若者セミナーが、業務の分野に限らず、仕事のやりがいや、ぶつかっている壁、ジレンマ、目標など、誰もが通る道、感じることを、語り合い、共感し合う場となり、新たな気づきから明日の実践につながるものになれば、と願っています。